ショッパー・マーケティング研究会 2025年度
売場・店舗のトレンド動向と、買い物行動への情報力を高める(消費財メーカー・卸売業を対象)
研究会の進め方・スケジュール
研究会の進め方
2025年6月~2026年3月にかけて計8回の定例報告会を開催します。研究員による報告のほか、効果的な販売・マーケティング活動を展開する有力実務家をゲストに招き、取り組み内容を報告いただきます。
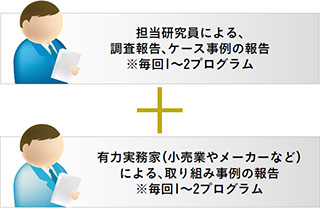
報告会への参加方法について
研究報告会に参加できる人数の制限はありません。各プログラムごとに関心のある方にご参加いただけます。
※2024年度は営業パーソンを中心に、約1100名に聴講・参画いただきました(延べ人数)
【※聴講方法について】
報告会へのご参加では、「① 会場聴講」と「②WEB聴講」を選択いただけます。参加者によって会場聴講とWEB聴講を併用することも可能です。
※WEB聴講においては支社・支店の方にも多く聴講いただいております
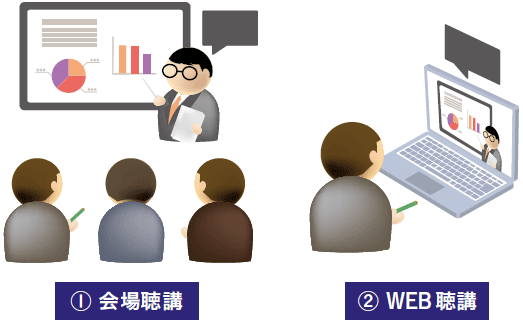
2024年度 研究報告会のスケジュール予定など
参加対象とアウトプット
原則として、消費財メーカーおよび卸売業を参加対象としたプログラムです。
- 各報告会ではテキスト冊子を配布するほか、研究会専用のホームページに資料ファイル(PDF、エクセル)をアップします。
- 毎年実施する「消費者の業態・店舗選択に関する調査」につきましては、自社でクロス集計できる機能が付いたファイル形式で提供します。
ショッパー・マーケティング研究会は2011年度よりスタートし、本年度で14年目を迎えます。2023年度研究会では大手消費財メーカーを中心に計21社にご参画いただきました。
研究会報告会 開催予定日
- 第1回 : 2025年6月13日(金)
- 第2回 : 2025年7月25日(金)
- 第3回 : 2025年9月5日(金)
- 第4回 : 2025年10月10日(金)
- 第5回 : 2025年11月中旬[オンデマンドPRG]
- 第6回 : 2025年12月12日(金)
- 第7回 : 2026年1月23日(金)
- 第8回 : 2026年3月13日(金)
プログラムに関する追記 :
第5回目のところで、取引先顧客である「小売企業を見る視点」をレクチャーする視聴プログラム(オンデマンド聴講)を企画しております。
小売企業の決算短信(損益計算書など)の数値から、その企業の特徴や課題を理解してもらう構成です。
小売企業の2025年度上期決算が10~11月に公表されるので、最新の業績数値もケーススタディに用います。
研究会事務局
池田 満寿次
流通経済研究所 上席研究員 / 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト
※本研究会の主幹コーディネーター
- 主な研究領域:
小売・流通動向や、消費者心理、個人消費に関する研究。および、ネットスーパーやEC での購買行動に関する研究。 ※日本認知心理学会に所属。 - 経歴:
同志社大学法学部卒業。新聞社、人事・教育コンサルティング企業、マーケティング専門出版社の編集職を経て、2010年入所。 - 主な著書・論文:
『ショッパー・マー ケティング』日本経済新聞出版社2011年(共著)、『インストア・マーチャンダイジング 第2版』日本経済新聞出版社 2016年(共著)、「ショッパーの買い物意識と店舗選択の基準」、『流通情報』2017年5月、「個人消費の動向と展望について」、『流通情報』2018年1月(No.530)、「コロナ下、物価高―激変が続く環境下での買い物意識の変化と注目ポイント」『流通情報』2023年3月(No.561)など。
+
 研究会の協力パートナー
研究会の協力パートナー
小売企業の最新動向・事情をキャッチアップすべく、専門メディア(日経MJなど)の編集者らに協力パートナーとして、関わって頂いております(プログラム企画や、実際にスピーカーを務めていただくことも)。
