出版・情報サービス
機関誌「流通情報」
ISSN 2433-9784(オンライン)
ISSN 0389-7672(冊子版)
「流通情報」は、流通経済研究所の機関誌として1967年に創刊した雑誌です。現在隔月刊で発行しておりますが、流通・マーケティングの専門誌として評価をいただいております。内容は、流通・マーケティング関連の最先端の論文や、当研究所の研究報告、業界動向を流通・マーケティングの視点から抄録したもの等を掲載しています。
隔月刊:年6号発行、A4版 約100頁
年間購読料:30,000円(税込33,000円)[Web誌面閲覧サービス含む]
購読者サービス
※2017年1月発行号から最新号までの論文・記事がPDFで読み放題
「流通情報」最新号 目次
No.576 | Vol.57 No.3(2025年9月発行)
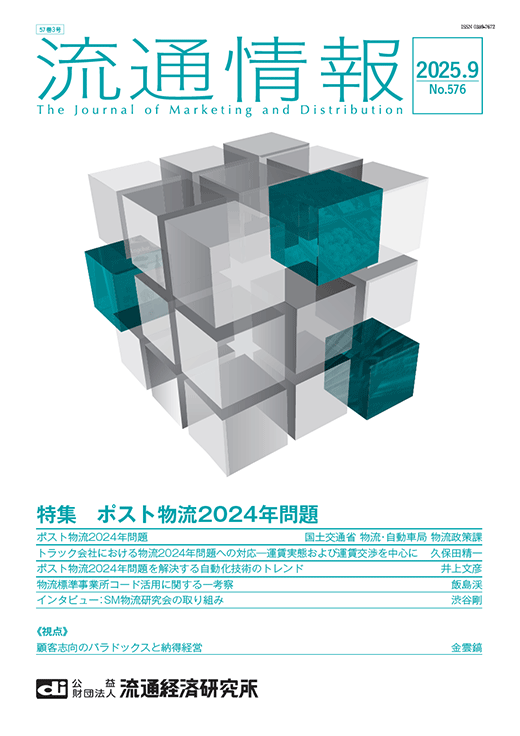
特集 ポスト物流2024年問題
特集にあたって
田代 英男
公益財団法人流通経済研究所 サプライチェーン部門 部門長/上席研究員
ポスト物流2024年問題
国土交通省 物流・自動車局 物流政策課
-
いわゆる物流の「2024年問題」に対応するため、一昨年6月に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」で決定された「物流革新に向けた政策パッケージ」等に基づき、①商慣行の見直し、②物流の効率化、③荷主・消費者の行動変容を三本柱とした抜本的・総合的な対策を講じてきた。政策パッケージに基づく官民での取組の成果により、現時点では物流の機能は維持できているが、物流の「2024年問題」は喫緊の課題であると同時に、年々深刻化していく構造的な課題である。2030年度に見込まれる34%の輸送力不足に対応するため、「新モーダルシフトの推進」、「物流拠点の整備」、「トラック・物流Gメンの執行強化」をはじめとする取組の一層の強化を図るとともに、物流全体の適正化や生産性向上、自動運転等の抜本的なイノベーションに向けて、次期「総合物流施策大綱」の策定に向けて検討を進める。
キーワード: 物流効率化法、物流の2024年問題、物流革新に向けた政策パッケージ、次期「総合物流施策大綱」、物流政策
トラック会社における物流2024年問題への対応
―運賃実態および運賃交渉を中心に
久保田 精一
合同会社サプライチェーン・ロジスティクス研究所 代表
-
物流の2024年問題を契機に、トラック運送業界では労働時間短縮と運賃是正が求められているが、特に中小企業では実態に即さない契約が依然として多い。本稿では、運賃交渉の実施状況や契約形態の実例を通じて、業界に根付く構造的課題を明らかにし、改善に向けた方策を検討する。
キーワード: 2024年問題、運賃交渉、中小トラック運送会社、標準的な運賃、改善基準告示
ポスト物流2024年問題を解決する自動化技術のトレンド
井上 文彦
株式会社NX 総合研究所 リサーチ&コンサルティングユニット4
-
物流2024年問題への対策について、その解決手段の1つとして自動化技術の導入が挙げられる。自動化技術といっても、物流ではその導入に様々な障壁がある。ただ、これから20年、30年を見据えるとこれまでのように人だけに頼ることはできない。また昨今ではAIなどを筆頭に人を代替する(場合によっては人より優れた)技術の発展は目ざましい。そこで、本論では、物流における自動化技術にフォーカスし、活用可能性のある技術の特徴は何か、導入に際してどのような考え方で進めるのがよいのかを考察する。
キーワード: 自動化技術、GTP、 AMR、 認識、予測
物流標準事業所コード活用に関する一考察
飯島 渓
公益財団法人流通経済研究所 研究員
-
近年、物流業界では深刻な人手不足や輸送コスト上昇、いわゆる2024年問題など構造的課題が顕在化し、効率化・省力化の実現が急務となっている。なかでも、物流拠点を特定する事業所コードにおける統一性の欠如、管理の煩雑さ、デジタル化の遅れは、情報共有や業務自動化の大きな阻害要因である。本稿では、物流標準事業所コードに関する現状課題を整理し、流通経済研究所が実施した取組みを通じて、名寄せ作業の実態と妨げとなる要因を明らかにした。さらに、物流事業者・荷主が段階的に標準コードを導入するための運用モデルや、制度整備・業界連携の方向性を提示したい。
キーワード: 物流標準事業所コード、共同配送、フィジカルインターネット、標準化、2024年問題
インタビュー:SM物流研究会の取り組み
渋谷 剛
SM 物流研究会/株式会社ライフコーポレーション 首都圏PC・物流本部 本部長
聞き手 田代 英男
公益財団法人流通経済研究所 サプライチェーン部門 部門長/上席研究員
-
「SM物流研究会」は、持続可能な食品物流構築に向けてサプライチェーン全体(製・配・販)で協議している。2024年度は主に、①パレット納品の拡大、②共同配送、③生鮮物流における課題の解決、④チルド物流における課題の解決についての取り組みを行った。2025年度は4つの取り組みを継続するとともに、荷待ち・荷役作業等時間の短縮ならびに改正物流効率化法の施行への対応、関西地方での物流課題の研究、課題解決に取り組んでいる。
キーワード: 協力領域、荷待ち・荷役作業等時間2時間以内、パレットサイズの非統一、共同配送、生鮮・チルド物流
ご案内
『消費者購買行動年鑑2025』
視点
顧客志向のパラドックスと納得経営
金 雲鎬
中央大学 戦略経営研究科 教授
資料紹介
海外の流通&マーケティング
流通データ
- 主要経済指標
- スーパーマーケット販売統計
- 主要家計指標
- コンビニエンスストア販売統計
- 百貨店統計
- ドラッグストア販売統計
- 日本チェーンストア協会販売統計
- 家電量販店販売統計
- ホームセンター販売統計
- 研究会・セミナーより
- 新着図書情報
次号予定:
特集 食品サプライチェーンのサステナビリティ経営(仮)
資料請求・お問い合わせ
資料請求・お問い合わせフォームお問い合わせ先
資料情報センター TEL:03-5213-4531(代表) FAX:03-5276-5457